 煎茶道
煎茶道 煎茶道具「茶敷」「茶具褥」
煎茶席に置いて用いられる煎茶道具「茶具褥」についてご紹介させていただきます※参考:煎茶全書 主婦の友社 昭和49年名称や扱い方は、流派や先生によって異なる可能性があります。煎茶道具「茶具褥」(ちゃぐじょく)煎茶道具「茶具褥」(ちゃぐじょく)...
 煎茶道
煎茶道  事例集
事例集 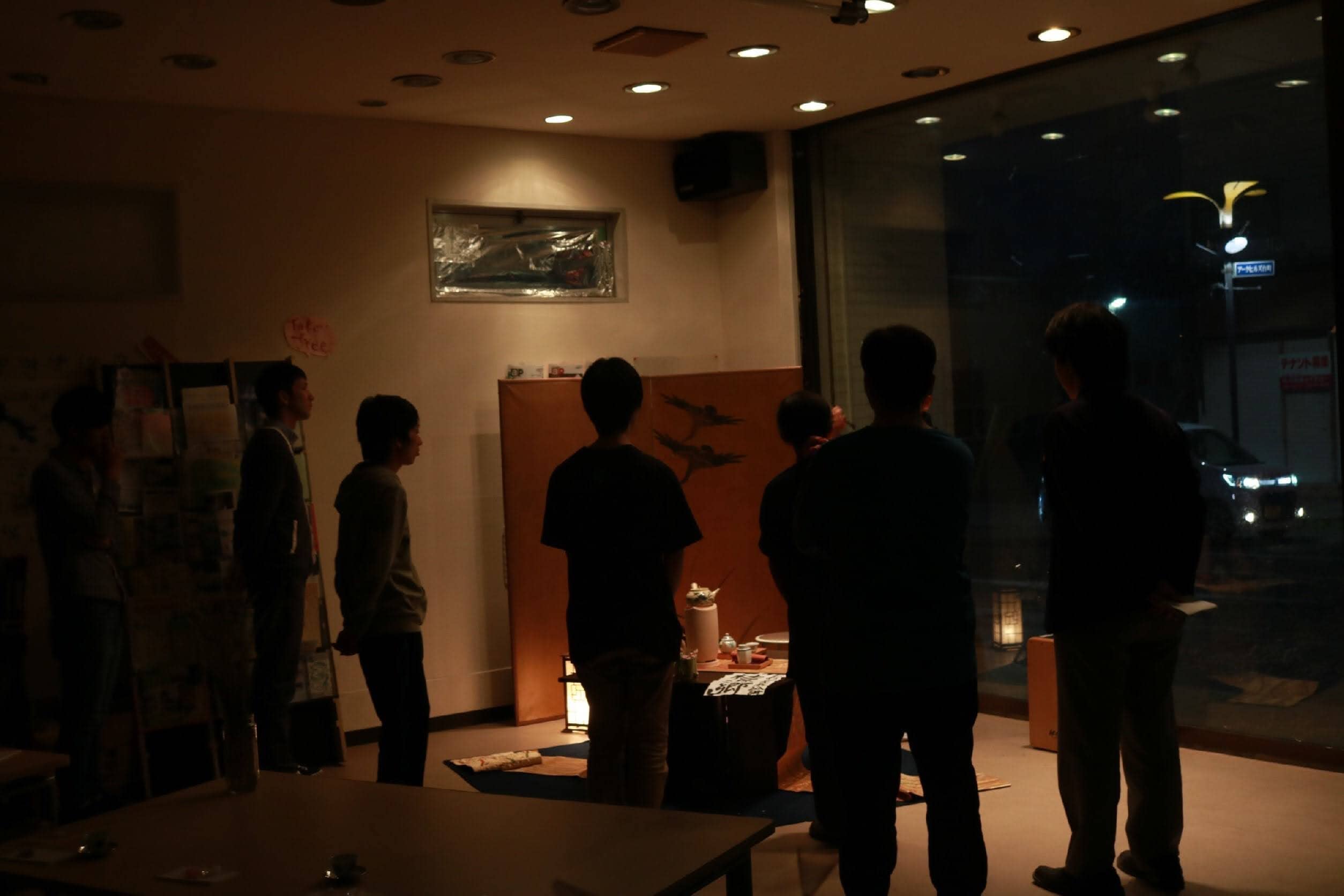 事例集
事例集  事例集
事例集  事例集
事例集  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道 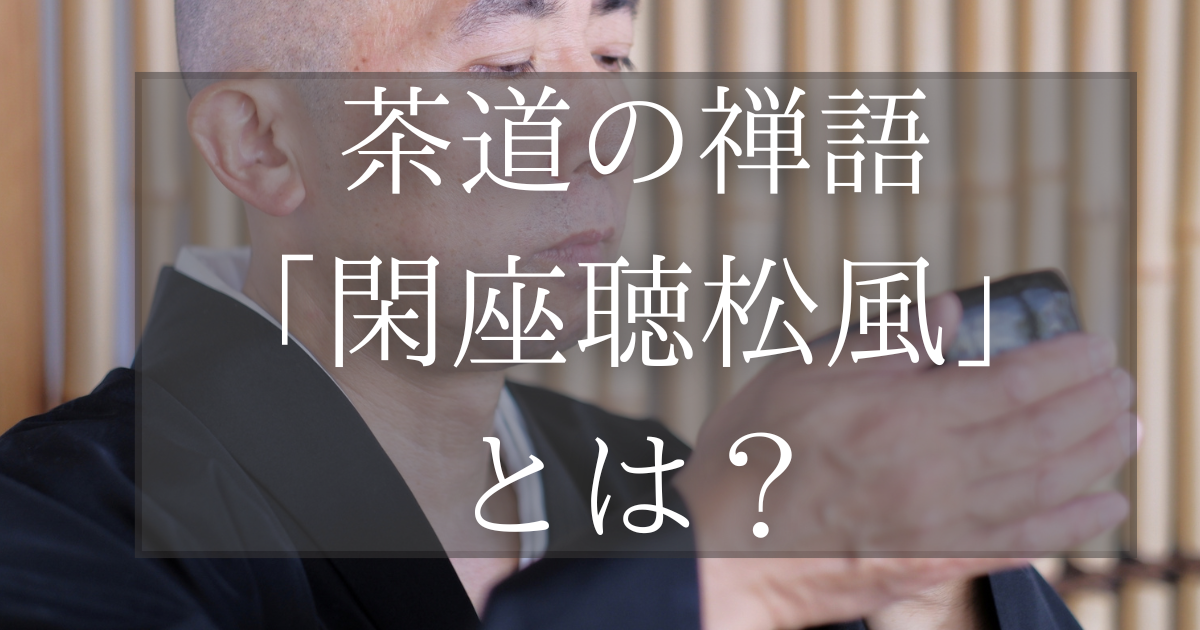 煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道