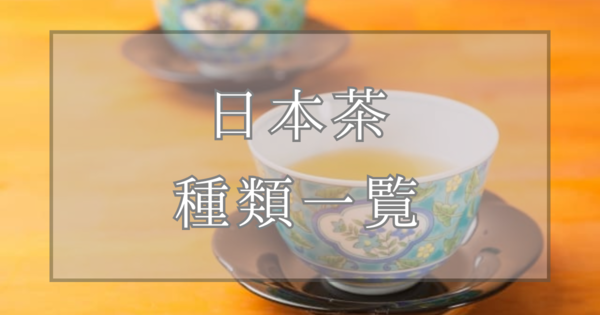石衣の読み方と意味
「石衣(いしごろも)」は、日本の伝統的な和菓子の一つで、読み方は「いしごろも」と読みます。名前の由来は、外見が石に衣(ころも)をまとったような姿に似ていることから来ています。特に見た目の素朴さと、甘さの控えめな味わいが特徴的で、茶道・煎茶道の茶席や贈り物としても重宝されています。
石衣と松露の違い2
石衣とよく似た和菓子に「松露(しょうろ)」があります。どちらも外側に粉状のものをまとった小さな和菓子ですが、細かい違いがあります。
- 外見の違い
石衣は、名前の通り石をイメージさせる外見で、衣(粉糖や和三盆)をまとったものが多いです。対して、松露は「松露(松の露)」というキノコの名前に由来し、やや丸みを帯びた形状が特徴です。 - 材料の違い
石衣の中身には、白あんや栗あんが使われることが多く、シンプルな風味が楽しめます。松露は、砂糖を使ったあんや小豆を主成分とすることが多く、甘さがしっかりと感じられる傾向にあります。 - 作り方の違い
石衣は、あんを丸めて衣をまぶすという非常にシンプルな作り方です。一方、松露は、砂糖を煮詰めてあんに絡める製法が特徴で、少し手間がかかります。
まとめ
- 石衣:見た目が石のようで、衣をまとっている。白あんや栗あんが使われる。
- 松露:キノコの松露に似た形。砂糖を使ったあんが多く、甘さが際立つ。
石衣の作り方・レシピ
石衣はシンプルな材料と工程で作ることができ、家庭でも気軽に挑戦できます。以下に、白あんを使った基本的な石衣のレシピをご紹介します。
材料(10個分)
- 白あん:100g
- 和三盆糖または粉砂糖:適量
- 栗あん(お好みで):100g
- 塩:少々
作り方
- あんを丸める
白あんや栗あんを適当な大きさ(約10gずつ)に分けて、手で丸めます。 - 和三盆糖をまぶす
丸めたあんを、用意した和三盆糖または粉砂糖にしっかりと転がして、まんべんなく衣をつけます。 - 冷やす
衣をまとったあんを冷蔵庫でしばらく冷やし、形を整えます。 - 仕上げ
出来上がった石衣を器に盛り付けて、完成です。茶席やおもてなしにぴったりな一品となります。
ポイント:白あんや栗あんの代わりに抹茶あんや紫芋あんなど、さまざまなフレーバーを使ってアレンジも可能です。
石衣の楽しみ方
石衣は、シンプルな風味が特徴の和菓子なので、抹茶など日本茶と相性が抜群です。また、上品な甘さのため、贈り物としても喜ばれます。お茶会の場や季節の挨拶として、おしゃれな和菓子箱に入れて手土産としても最適です。
まとめ
石衣(いしごろも)は、白あんや栗あんを衣で包んだ日本の伝統的な和菓子で、見た目が石に似ていることからその名が付けられました。松露(しょうろ)との違いは材料や製法にあり、松露の方が甘さが強いのが特徴です。
石衣の作り方はとてもシンプルで、家庭でも手軽に作ることができます。茶席や贈り物にもぴったりなこの和菓子、ぜひ一度作って楽しんでみてはいかがでしょうか?
投稿者プロフィール

- 日本茶講師/和文化PR
- 大学卒業後、老舗和菓子屋に入社。京都にて茶道、生け花、日本画を学び、日本文化への造詣を深める。和菓子屋での経験を活かし、その後、日本文化専門のマーケティング会社に勤務。現在はフリーランスの茶人として活動しながら、伝統と現代を結びつける活動を通じて、日本文化の魅力を広めている。
最新の投稿
- 2025年3月31日パワースポット大阪阿倍野パワースポット安倍晴明神社のご利益とは?やばいって噂は本当?なんの神様?阿倍王子神社との関係、京都の晴明神社の違い、アクセス方法を解説!
- 2025年3月30日パワースポット佐倉市パワースポット麻賀多神社のご利益とは?なんの神様?お守り情報、見どころ、由緒、ユダヤとの関係、アクセス方法や駐車場情報を解説!
- 2025年3月30日パワースポットパワースポット宮崎神宮のご利益とは?なんの神様?お守りや御朱印、歴史、アクセス、駐車場など解説!
- 2025年3月30日パワースポット吉祥寺のパワースポット神社「武蔵野八幡宮」のご利益とは?なんの神様?厄払い、スピリチュアルな不思議体験、レビューや評判、アクセス方法を解説!