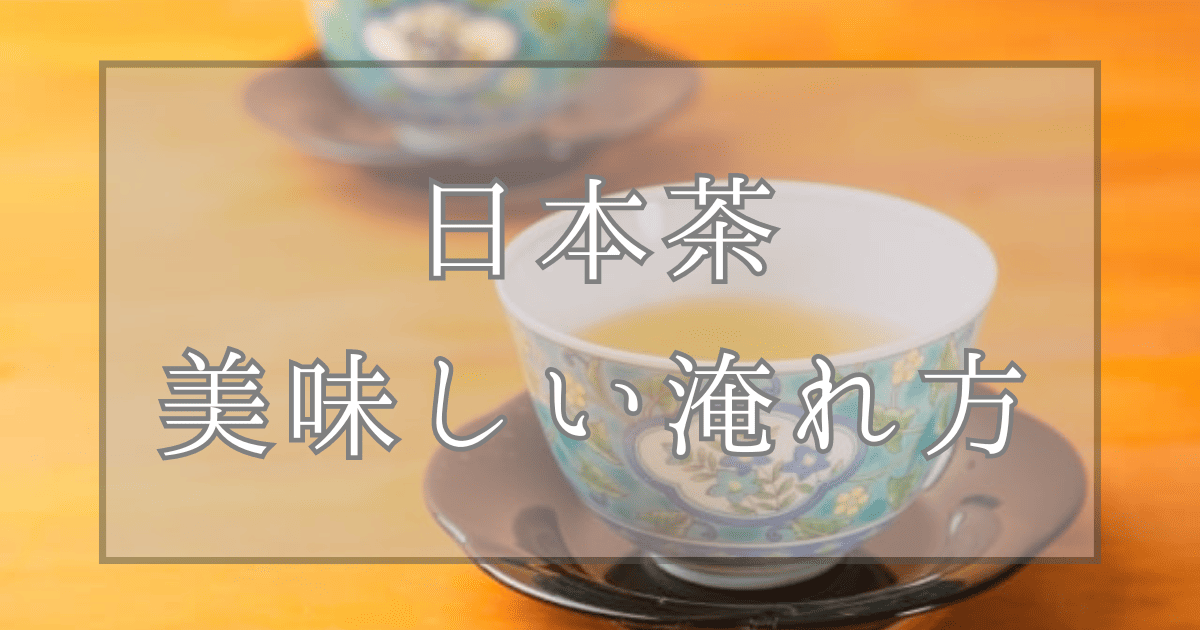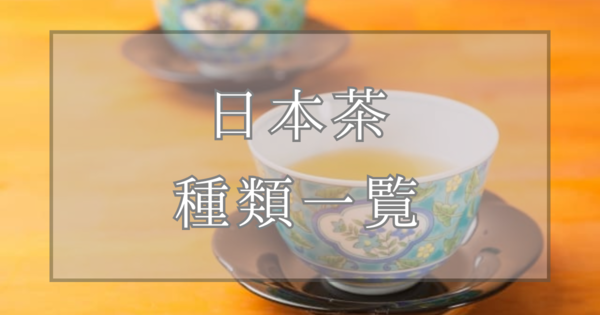嬉野茶とは
嬉野茶とは、佐賀県嬉野市を中心に、長崎県東部エリアで生産されている釜炒り日本茶です。
同じ釜炒り茶は、宮崎県のみやざき茶が有名です。
嬉野茶の特徴とは
嬉野茶の特徴は、茶葉に見られる形状で、独特の丸みを帯びた形にあります。
茶葉そのものがクルっと丸まっており、その見た目から、地元の人たちからは、「玉緑茶(たまりょくちゃ)」や「グリ茶」、「蒸しぐり」とも呼ばれています。
嬉野茶の製茶工程
嬉野茶は、製茶の過程において、ほとんど煎茶と一緒ですが、茶葉をまっすぐ伸ばす精揉(せいじゅう)の工程がないため、このような形状になります。
嬉野茶はどんな味?
嬉野茶は、玉露や煎茶と比べて、コクのある旨味が特徴で、香りが強いと言われています。
そのため和菓子の羊羹や饅頭と相性が良いです。
嬉野茶の歴史
嬉野茶の歴史は、12世紀に、臨済宗の禅僧である栄西が中国から持ち帰った茶ノ木から始まったと言われています。その後、たびたび中国大陸から渡来してくる唐人から、釜炒り茶の製法が伝えられました。
お茶を本格的に栽培したのは、1191年(平安時代)に、栄西禅師が佐賀県吉野ヶ里町の山腹に宋の国(中国)から持ち帰った種を播いたのが始まり、と言われています。うれしの茶の歴史は、1440年(室町時代)に中国大陸から移住した唐人により、嬉野町上不動皿屋谷で自家用に栽培されたのが始まりで、1504年(室町時代)には明から渡来した陶工「紅令民(こう れいみん)」が南京釜を持ち込み、釜炒り茶の製法を伝授したと言われています。
佐賀県嬉野市公式ホームページ:https://www.city.ureshino.lg.jp/kanko/ureshinocha/_19851/_19852.html
嬉野茶の美味しい淹れ方
嬉野茶は、茶葉の量や水の温度などで美味しく淹れることができます。
日本茶の美味しい淹れ方はこちらの記事をご覧ください。
日本茶好きにおすすめ関連記事
佐賀県の嬉野茶の記事はいかがでしたでしょうか。
九州には他にも宮崎県のみやざき茶や、鹿児島県の知覧茶など、緑茶の産地がたくさんあります。
さらに日本茶に興味を持たれた方はこちらの記事をご覧ください。
投稿者プロフィール

- 日本茶講師/和文化PR
- 大学卒業後、老舗和菓子屋に入社。京都にて茶道、生け花、日本画を学び、日本文化への造詣を深める。和菓子屋での経験を活かし、その後、日本文化専門のマーケティング会社に勤務。現在はフリーランスの茶人として活動しながら、伝統と現代を結びつける活動を通じて、日本文化の魅力を広めている。
最新の投稿
- 2025年3月31日パワースポット大阪阿倍野パワースポット安倍晴明神社のご利益とは?やばいって噂は本当?なんの神様?阿倍王子神社との関係、京都の晴明神社の違い、アクセス方法を解説!
- 2025年3月30日パワースポット佐倉市パワースポット麻賀多神社のご利益とは?なんの神様?お守り情報、見どころ、由緒、ユダヤとの関係、アクセス方法や駐車場情報を解説!
- 2025年3月30日パワースポットパワースポット宮崎神宮のご利益とは?なんの神様?お守りや御朱印、歴史、アクセス、駐車場など解説!
- 2025年3月30日パワースポット吉祥寺のパワースポット神社「武蔵野八幡宮」のご利益とは?なんの神様?厄払い、スピリチュアルな不思議体験、レビューや評判、アクセス方法を解説!