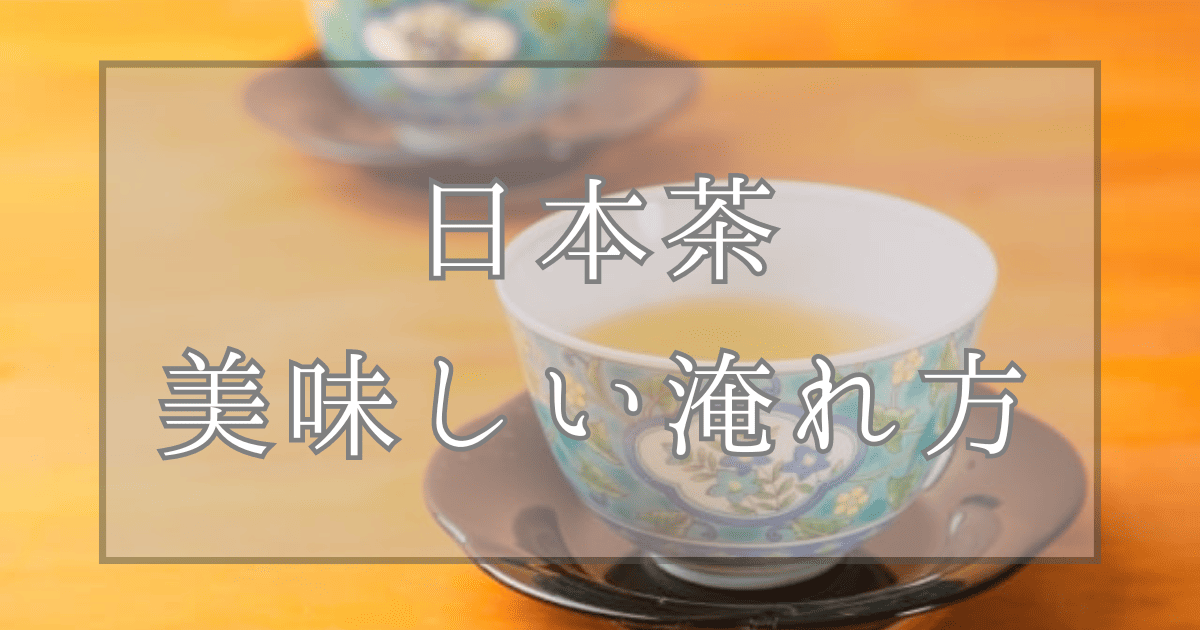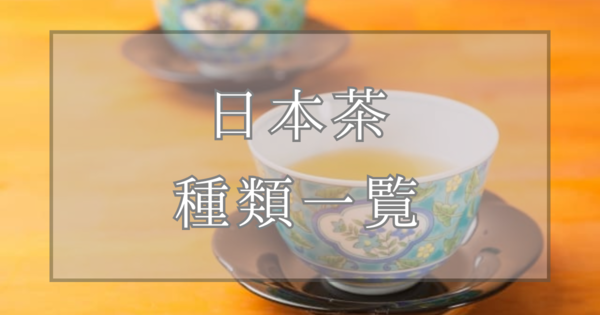宇治茶とは
宇治茶とは、京都府宇治市をはじめ、宇治田原町や木津川市、和束町や滋賀県、奈良県、三重県などの隣接県で生産される茶葉を、京都府内で加工した抹茶のことを言います。
また2004年には、宇治茶の基準が制定されており、以下のようになっています。
宇治茶は、歴史・文化・地理・気象等総合的な見地に鑑み、宇治茶として、ともに発展してきた当該産地である京都・奈良・滋賀・三重の四府県産茶で、京都府内業者が府内で仕上加工したものである。ただし、京都府産を優先するものとする。
引用:公益社団法人京都府茶業会議所
宇治茶の特徴とは
宇治茶の特徴とは、上品な香り、ほんのりとした甘味、すこし山吹色の水色、そして他の産地にはない宇治地方独特の風味です。宇治茶の味を出すためには、茶ノ木の肥料や手摘み採取など、手間暇をかけて生育しなければいけません。
味の秘訣は手摘みと肥料
高級宇治茶の特徴は、まず1年で最初に採れる一番摘みの緑茶が多く、それもハサミで刈らずに、手摘みで採取したものです。宇治茶は、京都山城地方独特の寒暖差が激しいところに発生する川霧や、適度な雨量など温暖な気候と、豊かな地味によって育まれた緑茶です。
また高級玉露や抹茶などは、普通緑茶の5~10倍の肥料を施し、光を遮って緑茶の苦みをおさえ、まろやかなお茶に仕上げます。高級な緑茶になりますと約95%くらい光をさえぎり、お茶の肥料だけで育てる訳ですから、何倍も肥料を施します。その遮光には棚を組み、かんれい紗で覆います。時としてその上に稲わらをふる場合もあります。このようにして丹精込めてつくられたものが、宇治茶なのです。
12世紀以降、連綿として800年間の歴史を刻む間に、宇治の地で洗練され、また茶道文化がその発展に更に磨きをかけました。
宇治茶の歴史とは
12世紀初頭、鎌倉時代に京都祇園にある建仁寺(けんにんじ)の禅僧である栄西(ようさい)が、中国から持ち帰ったお茶の種子は、京都北山にある栂尾(とがのお)で栽培され、その後、明恵上人(みょうけしょうにん)が宇治に栽培法とともに茶を伝えました。
さらに、日本独自のお茶の製法を完成させたのが、江戸時代、宇治田原に住んでいた永谷宗円(ながたにそうえん)という人物でした。彼が考案した「青製煎茶製法(あおせいせんちゃせいほう)」によって、お茶の品質が向上したため、京都の宇治茶は日本緑茶発祥の地として歴史に名を残すことになりました。
宇治茶の美味しい淹れ方
宇治茶を美味しく淹れるには、使用するお湯の温度や抹茶の量が重要になってきます。
抹茶を含め、日本茶を美味しく淹れたい方は、下記の記事も参考にご覧ください。
日本茶好きにおすすめ関連記事
宇治茶の記事はいかがでしたでしょうか。
宇治茶は、静岡茶や知覧茶と並ぶ日本三銘茶に数えられる緑茶です。
さらに日本茶に興味を持たれた方におすすめの記事をご紹介します。
投稿者プロフィール

- 日本茶講師/和文化PR
- 大学卒業後、老舗和菓子屋に入社。京都にて茶道、生け花、日本画を学び、日本文化への造詣を深める。和菓子屋での経験を活かし、その後、日本文化専門のマーケティング会社に勤務。現在はフリーランスの茶人として活動しながら、伝統と現代を結びつける活動を通じて、日本文化の魅力を広めている。
最新の投稿
- 2025年3月31日パワースポット大阪阿倍野パワースポット安倍晴明神社のご利益とは?やばいって噂は本当?なんの神様?阿倍王子神社との関係、京都の晴明神社の違い、アクセス方法を解説!
- 2025年3月30日パワースポット佐倉市パワースポット麻賀多神社のご利益とは?なんの神様?お守り情報、見どころ、由緒、ユダヤとの関係、アクセス方法や駐車場情報を解説!
- 2025年3月30日パワースポットパワースポット宮崎神宮のご利益とは?なんの神様?お守りや御朱印、歴史、アクセス、駐車場など解説!
- 2025年3月30日パワースポット吉祥寺のパワースポット神社「武蔵野八幡宮」のご利益とは?なんの神様?厄払い、スピリチュアルな不思議体験、レビューや評判、アクセス方法を解説!