 煎茶道
煎茶道 円山応挙とは?伊藤若冲と同じ時代に活躍した絵師の歴史や特徴、代表作を解説
京都の町絵師伊藤若冲と同時代に活躍した円山応挙(まるやまおうきょ)についてご紹介します。京都の町絵師として、世界的にも高い知名度を誇る伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)、若冲について調べていたら、どうやら同時代に池大雅(いけのたいが)や円山応挙...
 煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道 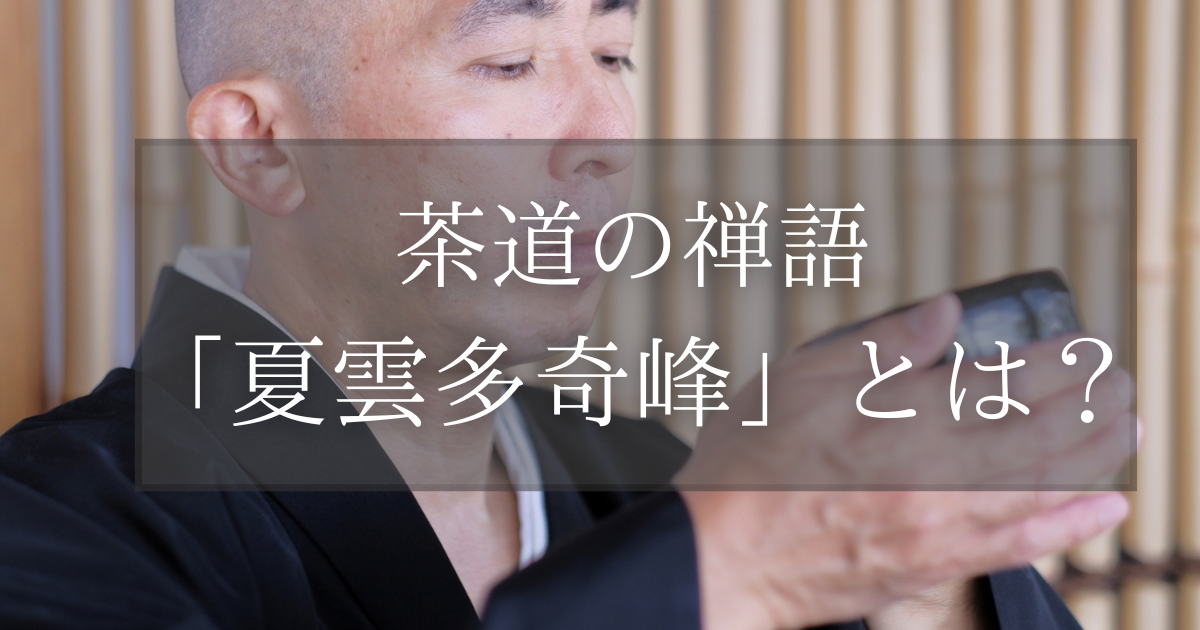 煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道