 地方文化
地方文化 大津絵の「鬼の寒念仏」の意味とは?読み方、なぜ鬼?販売店など紹介!
はじめに大津絵は、日本の伝統的な民画で、江戸時代から庶民に親しまれてきました。その中でも「鬼の寒念仏」は特に有名です。この絵にはどのような意味が込められているのでしょうか?本記事では、「鬼の寒念仏」の読み方や意味、なぜ鬼が描かれているのか、...
 地方文化
地方文化  民芸品
民芸品  民芸品
民芸品  民芸品
民芸品  民芸品
民芸品  民芸品
民芸品 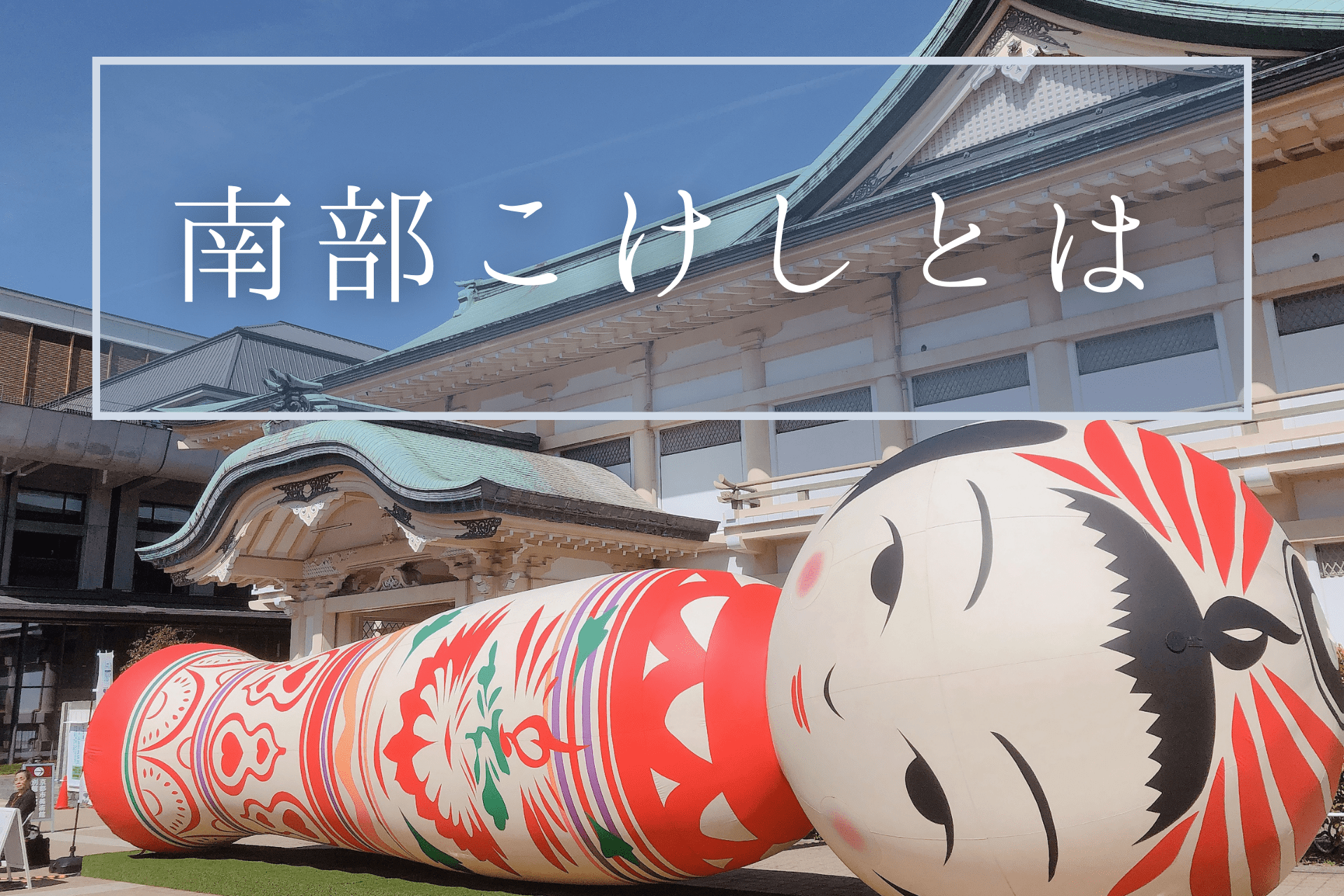 民芸品
民芸品 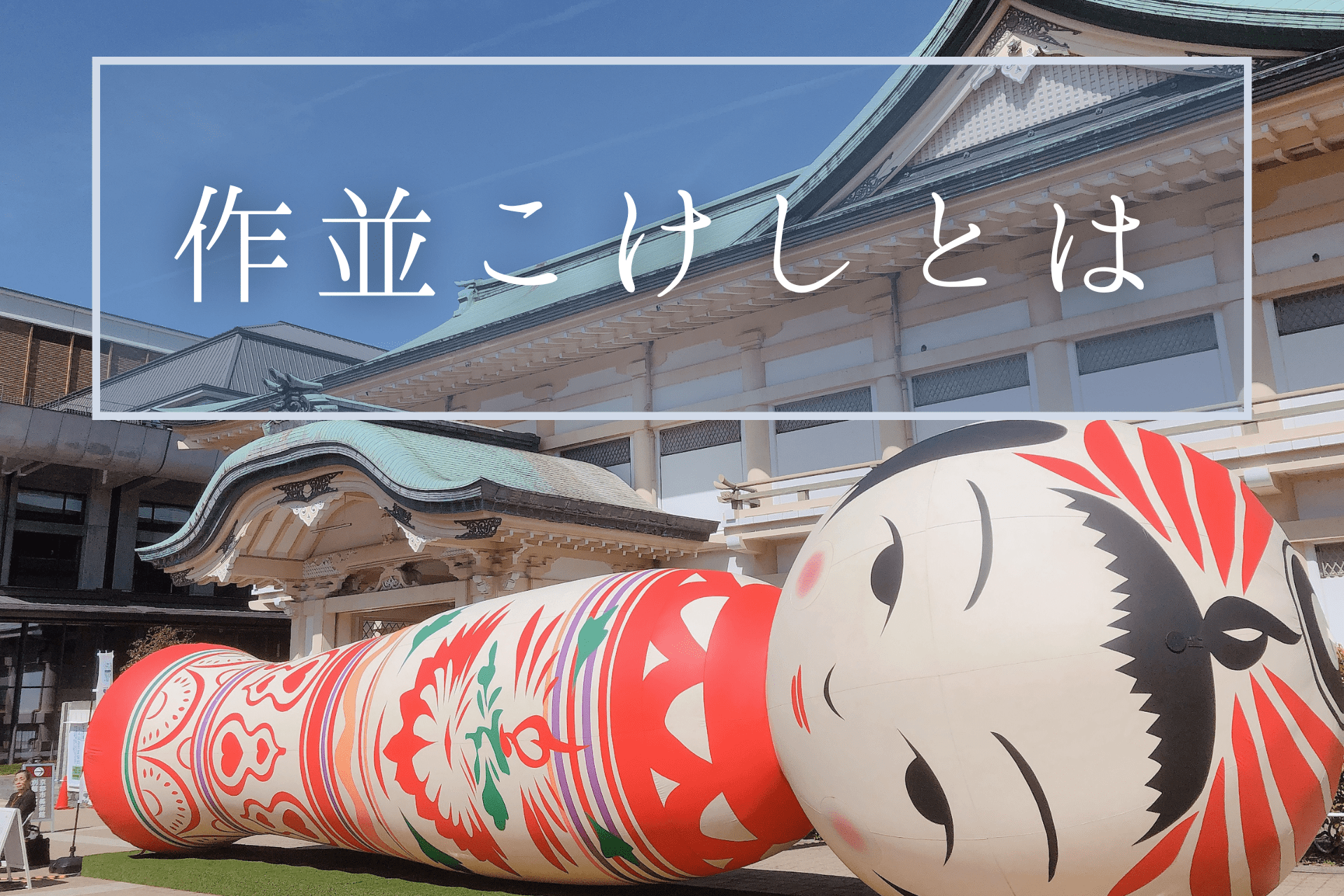 民芸品
民芸品  民芸品
民芸品  民芸品
民芸品