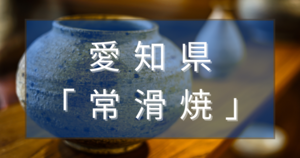 陶磁器・焼き物・器
陶磁器・焼き物・器 愛知県の常滑焼とは?特徴や読み方、歴史、名前の由来
愛知県の焼き物「常滑焼」の特徴や読み方、由来を紹介常滑焼という愛知県の焼き物の歴史や名前の由来、概要についてまとめた記事です。愛知県の常滑市(とこなめし)は、古くから続く焼き物の産地です。私の祖父母の家にもオレンジ色の急須があったりと、子供...
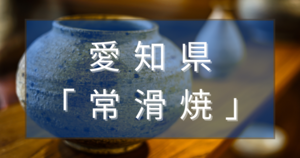 陶磁器・焼き物・器
陶磁器・焼き物・器  煎茶道
煎茶道  煎茶道
煎茶道  陶磁器・焼き物・器
陶磁器・焼き物・器  和菓子
和菓子  陶磁器・焼き物・器
陶磁器・焼き物・器  和菓子
和菓子  和菓子
和菓子  陶磁器・焼き物・器
陶磁器・焼き物・器  和菓子
和菓子